至誠の塔
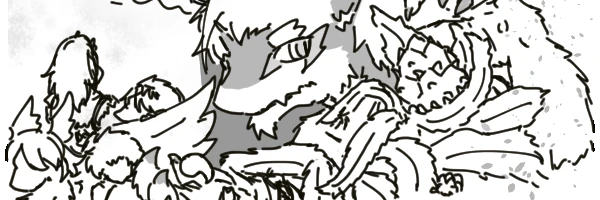
廻り廻った世界に集う、ドラコニダムのはじまりでおわりの物語
至誠の塔(しせいのとう)
Draconidum 25th 記念企画
250322-1話のみ先行公開, 250401-エイプリルフール企画で先行公開。現在連載中。
竜人たちの世界、アリアウト。雷禅リウスは見知らぬ世界で目を覚ます。6話完結、6人の主人公たちが織りなす、はじまりでおわりの物語。
ドラコニダムの入口的立ち位置、メインキャラ達のおおよそのイメージが掴める物語。これからはじまる、物語へ繋がる物語。
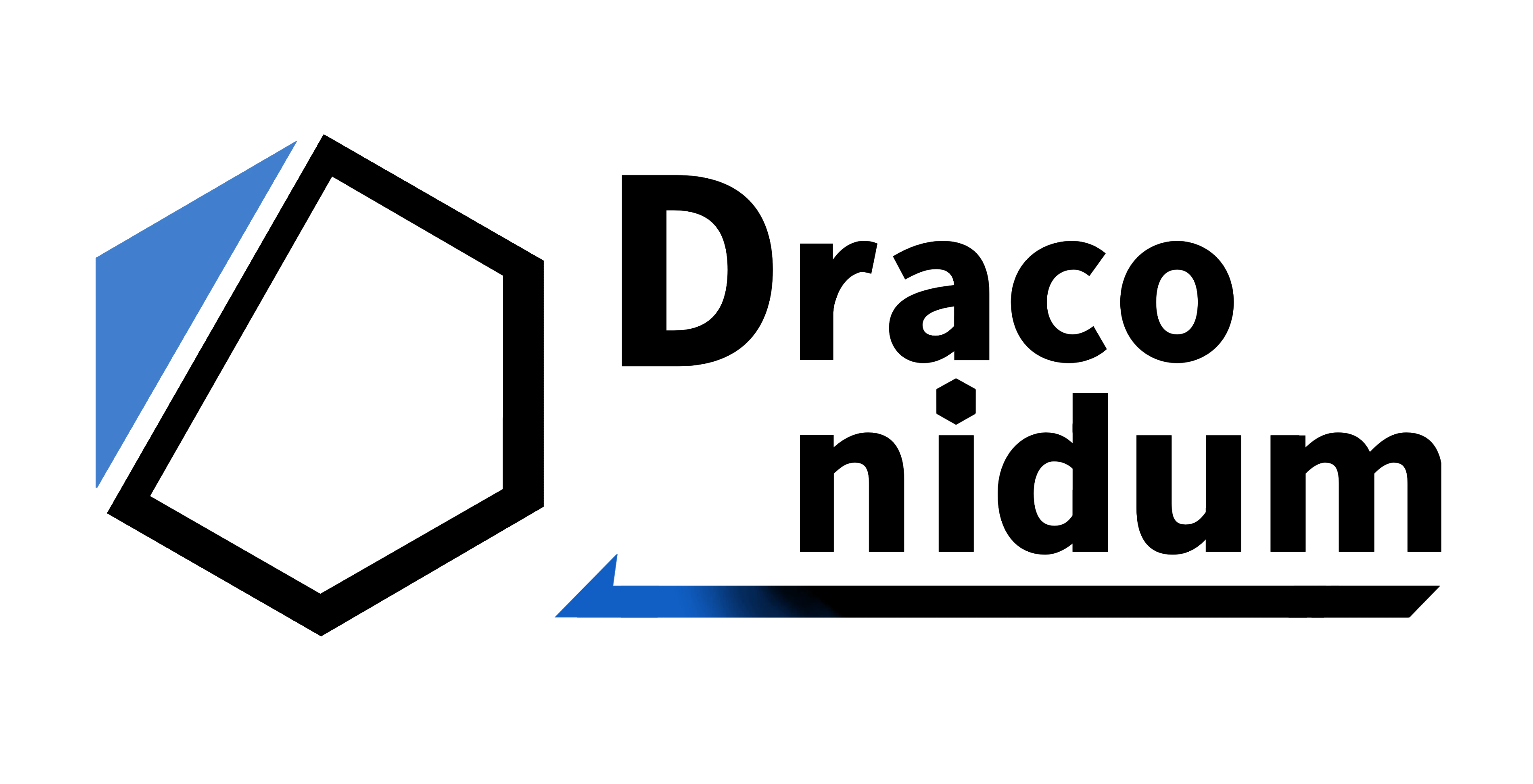
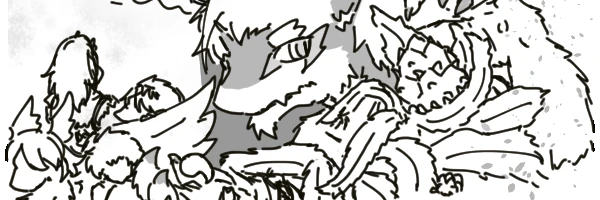
廻り廻った世界に集う、ドラコニダムのはじまりでおわりの物語
Draconidum 25th 記念企画
250322-1話のみ先行公開, 250401-エイプリルフール企画で先行公開。現在連載中。
竜人たちの世界、アリアウト。雷禅リウスは見知らぬ世界で目を覚ます。6話完結、6人の主人公たちが織りなす、はじまりでおわりの物語。
ドラコニダムの入口的立ち位置、メインキャラ達のおおよそのイメージが掴める物語。これからはじまる、物語へ繋がる物語。